 |
 |
 |
渥美郡
田原町
田原城は文明12年(1480年)頃、戸田宗光が築城。海に囲まれ、その湾の形から「巴江城」とも呼ばれていました。現在は石垣、堀などが残っており、公園整備されています。
地名はその土地を区画するために、昔の人々が付けた名前であり、人が住むところには必ず地名がある。
人は視覚的で固定性のある地形や地質、気候、生物、出来事などにより地名を付けている。
長い年月の間には、いつしかその意味も忘れられ、口から口へと語り継がれるうちに、呼びやすいように変化したり、誤字や脱字が生じたりすることもある。
古い時代に付けられた地名により、当時の人々の生活や、その当時の環境をしのぶこともできる。地名は実に貴重な郷土資料の一つともいえる。
単語や言葉の使い方、イントネーション(発声の抑揚)が標準語と異なり、ある地域でのみ使われる言葉を「方言」といい、いわゆる「なまり」もこれに含まれています。
方言は、それぞれの地域ごとに、長い年月をかけて語り継がれてきた大切な伝統文化なのです。「じゃん」、「だらあ」、「りん」に代表される三河弁ですが、「のんほい」、「まい」など独特の響きをもつ言葉もあります。一方では、渥美半島が太平洋と三河湾の二つの海に面している影響からか、「ど」、「くそ」など荒々しい口調の言葉もみられます。 「どべた(ど下手)」、「くそばか」などがその一例です。一般的に方言は、若い人より年輩の方、町部よりも農村部で多く使われているといえます。最近は標準語が一般化してきていますが、方言は一朝一夕で改まるものではありません。方言は郷土の証であり、その響きに愛着をおぼえる人も多いのではないでしょうか。
田原町では、昭和50年に2万6千人だった人口が、現在では3万6千人を超すに至っています。20年間で1万人、4割近くの人口が増えてきました。出身地は違っても、この町で暮らす人の数は着実に増えています。このような人たちに、田原の方言はどのように聞こえているのでしょうか。一方では核家族化が進み、方言を知らずに育っている子どももかなりいるのではないでしょうか。
蔵王山
田原のほぼ中央に位置する蔵王山。ドライブウェイ、権現の森からのハイキングロードで頂上に登ると展望台があり、穏やかな三河湾や波高い太平洋に囲まれた田原町が一望できます。
渡辺崋山
学者として、画家として、また政治家として活躍した渡辺崋山は、寛政5年(1793年)江戸の田原藩上屋敷で生まれました。
八歳から若君のお相手として出仕し、13歳の頃から鷹見星皐や佐藤一斎、松崎慊堂らに学び、朱子学や、陽明学をきわめました。
幼少の頃から画にも親しみ、すぐれたデッサン力をもとに、独特の描線と西洋画の遠近法などをとり入れ、多くの名作を世に送りだしました。
40歳で藩の家老職に就いてからは、田原藩の繁栄に貢献。「報民倉」を設け、天保の飢饉のときに一人も餓死者をださなかったことは有名です。
また一方では、高野長英らと西洋事情を研究し、鎖国の非を「慎機論」で記しましたが、幕府の批判とされ田原で蟄居を命ぜられてしまいました。藩に災いが及ぶのを恐れ自刃。享年49歳。
凧まつり
端午の節句に子どもの立身出世を願い初凧をあげたのがはじまりとされる「凧まつり」。毎年5月の第4土曜日・日曜日に開催されます。町の無形民俗文化財にも指定されている「けんか凧合戦」では、凧糸にガラスの粉を付けて、田原独特の横長の凧を自由自在に操り、鮮やかな糸さばきで互いの凧糸を切りあいます。
 |
黒河湿地植物群落 藤七原湿地植物群落 サンテパルク田原 吉胡貝塚 大アラコ古窯跡塗り代 ○蔵王山展望台 田原のほぼ中央に位置する蔵王山。ドライブウェイ、権現の森からのハイキングロードで頂上に登ると展望台があり、穏やかな三河湾や波高い太平洋に囲まれた田原町が一望できます。 |
化石産地 田原町、赤羽根町
表浜の海食崖の下部には、数十万年前の化石を含む泥層があり、堆積当時の自然環境を知る上
で貴重なヒントを与えてくれている。
赤羽根町高松海岸の泥層中には、下方に白い筋のように貝のつまったオオノガイ層があり、一
番上にはヤツシロガイの層が見られる。下から上への貝化石の種類の変化は、塩分の薄い内海か
ら浅くて広い砂質の外海への環境の移り変わりを示している。現在では護岸工事により泥層の下
部がおおわれてしまい観察が困難になっている。
田原町久美原海岸の泥層からは貝化石のほかブナ・タブ・カシ・モミ・ツガなど葉の植物化石
も採取できる。この当時は現在よりやや冷たい気候であったものと推定されている。
黒河湿地植物群落
この湿原は、おそらく渥美半島最大の湿原であろう。周囲にはシデコブシ群落やサクラバハンノキ群落がある。湿原中にはシラタマホシクサ・ミズギボウシ・ミカヅキグサ・ミズギクなどが生えている。その中でもヌマガヤと混生するヤチヤナギは貴重な植物である。ヤチヤナギは、本来東北
地方や北海道といった寒冷地に生えるものである。それが、温暖な渥美半島に見られる。多くの湿原では水不足による乾燥化が問題になっているが、ここではその心配もない。問題なのは土砂、特に栄養の多い畑の土の流入である。これによって富栄養化した湿原では、田圃の雑草が2㍍を越える高さで茂っている。
藤七原湿地植物群落
田原町藤七原のシデコブシ群落は、日本でも最大規模の群落である。世間に知られたのが遅かったため、現在は町の天然記念物になっているだけだが、この面積は魅力的である。この群落にはシデコブシのほかにノリウツギ・イヌツゲ・ハンノキ・ヘビノボラズなどのかん木が生えている。草本層にはヒトモトススキ・ヌマガヤ・サワシロギクなどが生えている。シデコブシ群落中にヒトモトススキが見られるのは、この藤七原だけであろう。ここでは遊歩道が整備され、シデコブシは保護されている。しかし、群落として考えれば、シデコブシ以外の他の木も大切なものである。その点で保護がやや行き過ぎている面もある。せっかくの遊歩道なので、ゆっくり回り、シデコブシ群落の良さをわかってほしいものである。
赤羽町
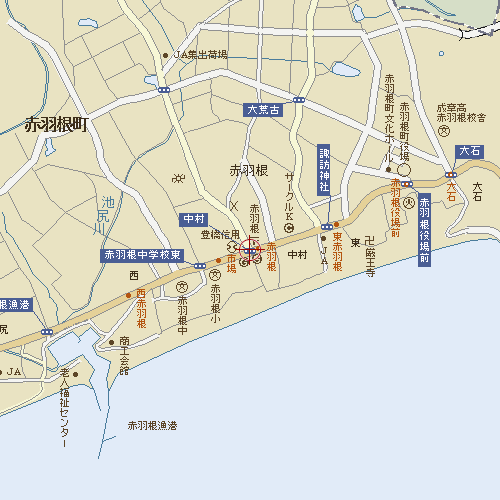 渥美半島の豊かな自然と温暖な気候に恵まれた赤羽根町は、昭和33年に町としての産声をあげ、住民一人ひとりが町づくりの主人公。「ちいさけれど住みよい町、大きなロマンを語れる町」・・・そんな「あかばね」を築いています。
渥美半島の豊かな自然と温暖な気候に恵まれた赤羽根町は、昭和33年に町としての産声をあげ、住民一人ひとりが町づくりの主人公。「ちいさけれど住みよい町、大きなロマンを語れる町」・・・そんな「あかばね」を築いています。
渥美半島の天伯原と呼ばれる台地は、太平洋側が最も高く北の三河湾に向かって低下し、南高北低の逆傾斜の地形になっている。また先端の伊良湖岬に向かって少しずつ低下している。これは曲隆運動と呼ばれるドーム状に盛り上がる隆起によって生じたもので、南の太平洋岸は長年の海岸浸食により流出している。田原町の太平洋岸には、海岸線に並行して2~3列の天伯原の原面が東西に細長く連続し、その間は深い開析谷が東西に走っている。強酸性の赤土と小砂利(天伯原礫層)からなるこの台地は、水に恵まれないため、昭和43年に豊川用水が通
水するまで開墾できずに放置されていた。現在では開発のため多くが原形をとどめていない。
表浜の砂の多くは、天竜川方面から西向きの沿岸流によってもたらされたものである。このことは赤羽根漁港の東西の砂浜を比較すればよくわか赤羽根漁港では太平洋に向かって延びた2本の堤防によって、沿岸流による砂の移動が止られてしまった。このため東の赤羽根側では砂浜が年々拡大した。供給が止まった西の若見側では砂浜が流出し、浸食を防ぐため護岸工事が続けられている。かつての表浜には、広い浜と小高い砂丘があった。近年砂浜はすっかり痩せ、テトラポットで波浪浸食を防ぐ工事が進られてきた。これは供給源の天竜川にいくつものダムが造られ、下流部での川砂の採取などより砂の供給量が著しく減少したことにある。
渥美半島の太平岸には片浜十三里と呼ばれる海食崖と砂浜が東西に一直線にのびている。この海食崖を構している砂礫の互層は、数十万年前に海底に堆積し、まだ十分に固まっていないので、浸食に極めて弱く、高さ10~70mほどの急峻な海崖になっている。山脚部が海岸まで迫る赤羽根西では、チャートを主体とする礫浜が発達している。特に渥美半島の先端部の伊良湖岬や日出にかけては、山脚部が波に削られ基盤岩が露出し、石門などの岩礁が点在し、渥美の観光シンボルともなっている。褶曲した層状チャートからなる石門の天井部には断層線が見られ、層でもろくなったこの部分が太平洋の荒波で掘削され海食洞になったことがわかる。
温室栽培による最初の作物は、果物の王様といわれるマスクメロンです。昭和10年からの実績を誇り、生産農家とJA農業技術センターとの協力体制により、赤羽根ブランドの確立をめざしています。また秋から翌年の初夏にかけては、温室トマトが栽培されています。電照菊に次ぐ生産量を誇り、全国各地に出荷されて、好評を博しています。このほか、夏菊やスプレー菊の生産量もたいへん大きく、全国的にも有名です。美しい菊の花は、花いっぱいのまち・赤羽根町の町花となっています。
徳川家康公が、長い戦国時代を平定し、江戸に幕府を開いた時、当時の世相を憂い、民政の安定と庶民救済の守り神として、国神を始め、印度、支那の名のある諸神をあつめて、人々に七難即滅、七福招来を与え、天下泰平をねがう庶民信仰として、広めたのが、七福神のはじまりと伝えられております。
東海七福神は、昭和33年に開眼し、三河湾国定公園に指定されている渥美半島にあります。名刹七ヶ寺に七福神を祀り、信仰と観光を兼ねて巡拝出来るようにしたものです。七福神巡拝によって、皆様方の生活の中から不安と不幸を除き、安心と幸福が授かれば、幸いだと願われています。
赤羽根町は太平洋に面した海のまちでもあります。赤羽根漁港を拠点にシラス漁や沖合でのサバ釣漁などが行われ、春から秋にかけての早朝は、出港するたくさんの漁船でにぎわいます。赤羽根漁港は昭和28年から整備が始まり、56年には水産物荷さばき場が完成、さらに水産加工場や給油所、東防波堤灯台などが整いつつあり、漁船漁業基地としての将来に期待がかかります。同時に「獲る漁業から育てる漁業へ」という考え方も定着。限りある資源を大切にし、自らの手で魚を育てていこうと、昭和33年頃から魚礁の設置が始まりました。コンクリートブロックによる魚の住みかは、現在15kmの沖合に達しています。このほか、地元の子どもたちなどを対象に、かつての漁業を体験するための地引網も行われています。
渥美町
渥美半島の人々を恐怖におとしいれたのは空襲だけではなかった。昭和19年12月7日13時36分ころ熊野灘沖を震源とするマグニチュード8の大地震が東海地方を襲った。「東南海地震」である。現渥美町の被害は全壊した建物約350棟、死者1名であった。さらに、翌昭和20年1月13日3時38分ころ渥美湾を震源とするマグニチュード7.1の「三河地震」が発生した。福江町では震度6の烈震、泉村・伊良湖岬村では震度5の強震であった。被害は全壊した建物約50棟、死者1名であった。2度の地震の被害は地盤の弱い福江町が最もひどく2名の犠牲者も福江町であった。
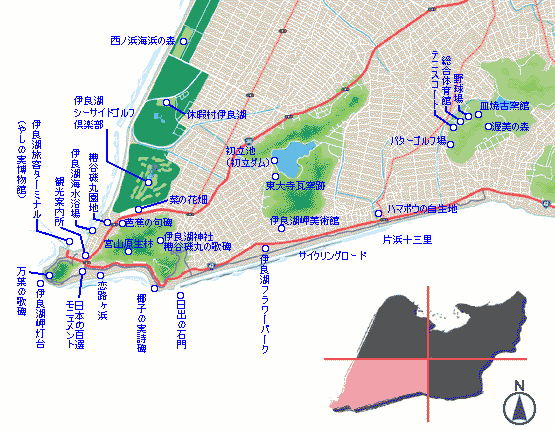
|
御衣祭は三河湾で取れた蚕糸を織って、伊勢神宮におんぞ料として献じたのが始まりといわれ、昭和42年までは、伊勢神宮の『神御衣祭(かんみぞのまつり)』と同じ、旧暦4月14日に行われていましたが、現在は4月の第3日曜日が祭礼の日と決められています。 この祭が行われる伊良湖神社はその昔、伊良湖久大明神といわれ、この地が伊勢神宮領伊良胡御厨(みくりや)であったことから、伊勢神宮とはたいへん縁が深く、社殿も神宮と同じ規模で、神事も外宮からねぎが来て執り行っていたそうです。 参道に露店が並び、参拝者や観光客でにぎわう祭の当日、付近の人々は習わしに従って、針やハサミを手にしません。 |
渥美町の歴史の歩みをさかのぼると、狩猟採取をよりどころに生活を営んでいた人々へつながります。考古学上知名度の高い伊川津・保美などの貝塚から、叉状研歯(さじょうけんし)等の人骨、有髯土偶(ゆうぜんどぐう)をはじめ、石器、土器、骨角器、獣骨、魚骨、貝がら等貴重な遺物が多数出土しています。これらから、縄文時代の生活様式や集落状況などをある程度うかがい知ることができます。
農耕のあけぼのと言われる弥生時代の遺跡は、小森、大本、羽根、保美などをはじめとして、町内30数か所に及び、集落の分散、人口の増加、農耕と狩猟を兼ねた暮らしなどを物語ってくれる。また、金属文化の流入を象徴する銅鏃(どうぞく)や銅鐸(どうたく)も後になって発見され、海を隔ててはいますが、畿内からの影響を知らせています。
また、古墳時代の群集墳が、藤原、馬越、沢山、志知羅、高木、塚土などの山麓や尾根、大地に構築されているのを見ると、この時代の人々が精力的な生活をしていたことが推測されます。
平城宮跡出土の木簡に「参河国渥美郡(みかわのくにあつみごおり)」と明確に読めるものが3枚、ほかに推定されるものが3枚検証されています。藤原宮跡出土の木簡とあわせて考察すると「飽海郡」を「渥美郡」と表記するようになったのは、和銅6年(713年)のこととみられます。
平安時代の編著になる和名抄に、渥美郡6郷の名が書かれていますが、本町の集落は和太郷、大壁郷の地域内であったことと思われます。
平安時代、全国的に荘園が増加拡大した時期に、これまで伊勢とのつながりが深かった本町の村々の多くが、伊勢神宮領になっていました。今に伝えられる「御厨(みくりや)七郷」がそれで、伊良湖、亀山、中山、畠(古田、高木を含む)、小塩津、保美、堀切の村々です。
平安末期から鎌倉時代の古窯跡として、国や県の史跡の指定を受けている伊良湖東大寺瓦窯跡や皿山古窯址群があります。これらの遺跡は、発掘調査されましたが、この時代の産業の一端を知る上で貴重なものです。
伊勢神宮領は、室町時代、公卿清閑寺幸房領から鳥丸資任領に移行したことが「建内記」に記されています。
戦国時代の本町は、田原城を築城した戸田弾正左衛門宗光の奥郡攻め、今川軍の半島攻略、家康の三河平定と乱世を背景に領主の変遷がありました。
江戸時代には、大名領、天領、旗本知行地、寺領と支配を異にしながら、地域の連帯と論争など複雑な村々の状況を呈していました。
幕末においては、伊川津、古田、畠、向山、亀山、日出の村々が大垣新田藩、和地、宇津江の一部は田原藩、中山、西堀切、高木の村々が旗本清水氏、江比間、宇津江の大部分と小塩津の一部が旗本諏訪氏、山田村は泉福寺領、八王子、村松、馬伏、石神、小塩津の一部が旗本本多氏、保美、東堀切、伊良湖の村々が幕府代官所支配(天領)でした。
明治4年7月の廃藩置県のあと、同年11月の改置府県のとき、三河全域と知多郡は額田県となりました。そして明治5年11月、額田県が愛知県と合併しました。その後、いくたびかの合併を経て、昭和30年4月15日、福江町、伊良湖岬村、泉村の1町2村が1つに結ばれ、渥美町が発足しました。
以来、恵まれた自然環境を生かして、農業、漁業、観光などが発展した風光明媚な温暖なまちです。
| 位置 愛知県の最南端、渥美半島の先端 | 人口 22,929人(平成15年2月28日現在) |
| 面積 82.18k㎡ | 世帯 5,960世帯(平成15年2月28日現在) |
| 気候 年平均気温16℃ 年平均降水量1,600㎜ | |
大アサリ
大アサリは水深10メートルくらいの海底に生息していますので素人ではまず取れません。地元の漁師さんが体を張ってひとつひとつ丁寧に取ってくるのです。
大アサリの生産高の全国一位は何と言っても愛知県!(10,2058t)全国シェアの27.6%を占めています。もちろん、愛知県の中でも一番の産地はやはり渥美町です。
鉄分を多く含み、貧血を予防する働きをします。
そして何と言ってもビタミンB1、B2は貝類の中でも特に多く、悪性の貧血に効果的です。
保存次第では5日~7日くらいは生きています。いろいろな食べ方がありますが私は、ただ単純に貝を二つに切って、それにネギ、醤油(お好みの量で)、酒(お好みの量で)、を加えて網の上で焼く方法をオススメします。
一番簡単で一番大アサリの美味しさがわかる食べ方だと思います。
渡り鳥
渥美半島の山林は全面積の半分近くが三河湾国定公園特別地域に指定されており人工工作物もこれまでは少なかった。
サシバは郡内3町の山林各所で繁殖しており、その数もタカ類の中では最も多い。しかし道路建設や土砂採取などで生息可能な環境は狭まっており、渥美でも減少傾向にある。
オオタカは渥美町の山林で繁殖が確認されているが、赤羽根町でもその可能性は大きい。両地域とも近くに開発構想が示されており将来が心配されている。ハチクマやフクロウ、アオバズク、小鳥類のオオルリ、サンコウチョウも繁殖が確実となっている。他に、近年個体数の激減で心配されるミサゴを始めハヤブサ、ツミなど数種のタカ類でも繁殖の可能性がある。
渥美半島におけるタカ渡りの中心は、春4月中旬~5月末、秋9月中旬~10月末で、秋期のワシタカ類の総数は、1万羽にのぼる。その中心はサシバだが、9月中はハチクマ、アカハラダカ、10中旬にかけてサシバ、チゴハヤブサ、その後にツミ、オオタカ、ハイタカ、期間全般にかけてノスリ、ミサゴを観察することができる。春の渡りはまだ不明な点が多く、日に数十~百前後のサシバと少数のハチクマが伊良湖岬などで観察されるに留まっている。冬季にはノスリ、チョウゲンボウ、ハイタカ、ハヤブサなどが越冬し、少数ではあるがオオワシ、オジロワシも記録されている。
伊良湖岬は、半島を通過するタカ類を含む渡り鳥の大部分が観察できる地点として余りにも有名であるが、そこから東に連なる渥美の山林は、これら猛禽類の渡りの際の重要な休憩地として、また大部分のタカの渡りに影響を与える上昇気流を生み出す地形として必要不可欠な存在である。
メロン
伊良湖岬の港湾センターに下りると、椰子の実博物館がある。正面の岬の小高い丘の下を海岸線に沿って石畳の広い遊歩道がある。岬の先端には、真っ白な伊良湖岬灯台が立つ。沖には三島由紀夫の「潮騒」の舞台となった、神島が見える。
伊良湖岬から神島まで4キロ米強。灯台の横の丘に登ると、沖を望む航路信号所の建物があり、伊良湖水道の航路を通る大型船の通過時間を示す、大きな一本針の時計が掛っており、面白い。遠州灘の方向に海岸線をたどると、恋路が浜に出る。丘の上にそびえる伊良湖ビューホテルが城のように美しく、映える。
メロンの栽培は、野菜、果実のなかで最もむずかしいといわれ、土の選択かん水(かん水量は時期および発育程度によって加減され、定植から開花までは多すぎないようにし、とくに夏季は最小限にする)、温度管理(昼間は28~32℃)、夜間は18~23℃程度として、15℃以下、35℃以上にならないようにする)等、長年の経験が必要であり、品種の改良、病気の防除、糖度の向上等、栽培技術の向上に官民一体となって努力が続けられており、その成果が今日の発展につながっている。
温室メロンの栽培は、ガラス温室がほとんどで、トマトや菊などの輪作として、夏場に作付けされる季節栽培(夏作栽培)方法と、メロン専業農家が行っている年間通しての周年栽培方法とあるが、県下においては量的には季節栽培が断然多く、周年栽培は渥美町・小坂井町・一宮町の専業農家にみられる。なお、季節栽培と周年栽培の相違点は以下表のとおりである。
果物の王様として珍重されている温室メロンが、県下で栽培されたのは、明治40年(1907年)に当時の渥美郡牟呂吉田村(現豊橋市)の中島駒次が6坪(約20平方メートル)の温室を作り、マスクメロンを栽培したのが最初だとされている。その後、愛知県でも大正天皇御即位記念として各種の宅地利用事業が実施され、その一つとして温室栽培が奨励指導された。その結果、各地で温室が建てられメロンが栽培されたが、これらのほとんどは試作の段階であった。しかし、これが今日の東三河温室園芸へのスタートとなったことは事実である。以降、戦時中には贅沢品となり、栽培の中断を余儀なくされた時期もあったなど、幾多の変遷をたどったが、栽培農家のたゆまぬ向上意欲によって、今日の隆盛を築くに至った。
電照菊
電照菊の栽培がスタートした頃に比べ、品種の改良もずいぶん進んだ。現在、渥美町で栽培されている電照菊のベスト1は「秀芳の力」という品種で、全体の89.6%にものぼっている。この品種は電照に適しているだけでなく、花形がよく、切ってから長持ちすることで、消費者のニーズをとらえた。気品があり、香りも高いこの白菊は、葬儀用に重宝されている。菊は葬儀用の生花や外花の必需品として年間を通して需要が多い。美しい白菊を1年中入手できるようになったのは、まさしく電照菊のお手柄なのだ。
大和時代に、中国から朝鮮を経て日本に伝えられた菊。905年に編集された「古今和歌集」にはすでに菊を詠んだ多くの歌が登場している。そのふくよかな香りと清楚な姿で、菊は古くから日本人に愛され続けてきた。また国花として、日本を代表する花でもある。日本人は祝い事に弔時にと、暮らしの中でも菊と親しんできた。そんな菊をハイテクと結びつけて、年中供給できるシステムを作り上げた電照栽培。暮れなずむ渥美町には、電照栽培の未来のように明るい光の帯がキラキラと輝いていた。
渥美町の電照菊は、名古屋市内はもとより、出荷高の60%以上をトラック便で東京に運んでいる。デリケートな花の出荷には、交通手段の利便性も欠かせない。渥美町の電照菊が日本一に成長するためには、どうやら輸送に便利な地の利も一役買っていたようだ。
豊橋市北島町の電照菊栽培技術が紹介される。やがて漁業に見切りをつけた漁師たちが次々に温室経営に転向し始め、渥美町の電照菊栽培は渥美半島全域に広がっていく。新しい産業にチャレンジする漁師の決断が、渥美町の新時代を切り拓いたのだ。
満州事変と太平洋戦争
満州事変がおこり、1937(昭和12)年には、日中戦争がはじまり、日本と中国は全面戦争に突入した。当初、日本軍が戦いを有利にすすめたが、中国軍の徹底抗戦により戦線が拡大し、戦争は長期化していった。
戦線の拡大と戦争の長期化は電力・石炭・石油などの資源を不足させた。政府は戦争を遂行するため 1938年(昭和13)、国家総動員法を制定し、総力戦のため生産力拡大をはかり、軍需優先の物資動員計画をたてた。1939年(昭和14)には労働力確保のため国民徴用令が公布され、一般国民が強制的に軍需産業に動員されるようになり、民需品の輸入や生産は制限された。
政府は「ぜいたくは敵だ」というスローガンのもとに厳しい経済統制をおこない、物資の不足によるインフレーションを抑制するために1939年(昭和14)、価格等統制令を公布して物価調整と増産をはかったが、生活物資の不足は国民生活を圧迫し、1940年(昭和15)以降砂糖・マッチ・木炭・衣料などが切符制となった。
食糧生産は労働力や生産資材の不足のために1939年(昭和14)をさかいに低下し、食糧難が深刻になっていた。農村では、1940(昭和15)年から政府が強制的に米を買い上げる供出制が実施され、1941年(昭和16)には米が配給制となった。
日中戦争の長期化は国家経済を悪化させ、国民の生活を苦しめるものとなっていった。そこで政府は事態の打開策として資源の確保をめざし、南方進出を実行した。しかし南方への進出はアメリカ・イギリスとの対立を深刻化させ、日本への石油輸出が禁止されるなどの経済制裁が強化され、ついに1941年(昭和16)12月8日、日本は米・英に宣戦を布告し太平洋戦争がはじまった。
米・英との戦争は国家の存亡をかけた総力戦となり、政府は戦争遂行のため人員や物資の運用をはかった。民需工場は軍需工場へ転用され、学生・生徒・未婚女性は不足した労働力をおぎなうために学徒の勤労動員による学徒勤労報国隊や15歳以上25歳未満の未婚の女子からなる女子挺身隊として軍需工場で働くこととなった。
勤労動員によって男子の多くは名古屋をはじめとする県内の軍需工場へ動員された。残存の男子のなかには豊橋市大崎地区の海軍飛行場・大清水地区の陸軍飛行場で、飛行場建設・高師原演習地の草刈りなどの勤労奉仕をおこなった者もいた。また成章中学の生徒は学徒勤労動員により学徒勤労報国隊として、日本曹達田原工場・小野田セメント田原工場・豊川海軍工廠に動員されている。
女子もまた女子挺身隊として豊川海軍工廠へ動員されたり、学徒勤労動員により福江女子実業学校(旧福江高等裁縫女学校)・田原女子実業学校(旧田原高等技芸女学校)の女生徒が豊川海軍工廠へ動員された。田原女子実業学校の生徒は、ほかに日本曹達田原工場・東洋通信機豊橋工場にも動員されている。さらに福江町の渥美航空機工業には福江国民学校高等科の生徒が動員されている。
軍需工場への動員ばかりではなく、労働力が不足していた農家への援農や食糧増産のための空閑地・荒廃地・運動場などの開墾がおこなわれ、多くの生徒が勤労報国隊として勤労奉仕をしている。また田口農林学校(愛知県立田口高等学校の前身)の生徒多数が援農として、各地区の国民学校に約10日間滞在して(福江国民学校には50名)勤労奉仕をしている。
ますますきびしく困難になってきた戦局のもとに、生徒たちも工員と同じく2直制になりました。早出勤は午前3時5分前起床、5時5分より作業開始、12時25分終了。おそ出勤は12時5分前起床、2時5分より作業開始、9時45分終了。この時間帯の中で私は、朝星夜星をあおぎながら若さにまかせ、勝利を信じ、生徒たちの無事を念じながら寝食を共にしました。粉骨砕身という字の如くに。警戒警報の発令も回数が多くなり、防空壕への避難やバケツリレー式の消火訓練も度々行われました。
仕事に行くときは、皆必勝の鉢巻をしめ、かばんを肩にかけ、医薬品の袋を持ち、もんぺを履き、防空頭布を被って出かけました。食糧は、イモの輪切りの炊き込みご飯、干したイモのつる、イナゴのつくだ煮等でした。時々、海軍の技術少尉さんがサツマイモをくれ、それがとてもおいしかったのを覚えています。さらに軍需物資の不足をおぎなうため鉄製品・貴金属・寺院の梵鐘までもが供出された。また兵士の不足をおぎなうため、1943(昭和18)年には学徒出陣がおこなわれ大学・高等学校・専門学校の学生・生徒の徴兵猶予を停止して、軍に召集した。その後、兵役法を改正し、兵役年齢を17歳まで引き下げ、1945(昭和20)年には国民義勇兵役法が公布され15~60歳の男子、17~40歳の女子を国民義勇戦闘隊に編成した。
しかしこれらの努力にもかかわらず戦局は悪化し、制海・制空権の喪失により、依存していた南方の物資も輸送が困難になり資材が極度に欠乏した。それに加えて1994(昭和19)年末からアメリカ空軍の爆撃機による本土空襲が激化して多くの犠牲者を出し主要都市や工場が破壊され、工業地帯は壊滅的な打撃をうけ工業生産力は急速に低下した。空襲の激化にともない地方へ婦女子の疎開や学童の集団疎開がおこなわれた。また食糧の生産力も低下し、戦局の悪化により東南アジア・台湾・満州・朝鮮からの食糧の輸送もとだえ、米の配給も削減され、食糧不足は一層深刻となった。こうして日本経済と国民生活は崩壊していった。
1945(昭和20)年にはいると日本の敗戦は濃厚となり、3月には硫黄島、6月には沖縄がアメリカ軍に占領された。アメリカ軍は8月6日に広島、8月9日に長崎に原子爆弾を投下し、8月8日、ソ連が日本に宣戦を布告した。日本の敗戦は決定的となった。ついに政府は8月15日ポツダム宣言を受諾して無条件降伏をし、戦争は終結した。