豊橋市
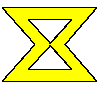 市のマークの由来
市のマークの由来
豊橋市徽章は、豊橋市の前身と言える旧吉田藩主が使用していた千切(ちぎり)を基礎としたもので、
長年豊橋を表象してきたため、これを襲用して明治42年6月6日、本市の徽章としました。
豊橋市の人口は約37万人。(平成15年)市域面積は 261.26k㎡です。
東は弓張山系を境に静岡県と接し、南は太平洋、西は三河湾に面しており、豊かな自然と温暖な気候に恵まれています。
吉田城は1505年に築城された今橋城が後に改称されたもので、現在は昭和29年に復興された隅櫓が豊川のほとりに建っています。豊橋公園内にあり、美術博物館、三の丸会館とともに多くの市民に親しまれています。
愛知県下第2の都市で東三河地方の中心。1906年市制。1955年二川町、石巻、前芝、高豊、老津の4村と、杉山村の一部、双和村の一部を編入。市の都市機能上の特色は第2次世界大戦前と戦後とで全く一変し、戦前は紡績とくに玉糸製糸工業と第15師団司令部の所在する軍都であった。1945年6月20日の大空襲により焼失し、全市の70%が灰になったが、戦後ただちに新構想による復興都市計画が行われ、見事な近代都市に生まれ変わった。
東海道本線・新幹線、飯田線、名古屋鉄道、豊橋鉄道が分岐し、市の北部を東名高速道路が通じる。このため商圏は東三河、浜名湖西、飯田盆地にまで伸長している。工業上は紡績の都市で、岡谷とともに製糸工業の核心都市であったが、現在も紡績が中心で、その他食料品(菓子、水産加工)、木材の比率が高い。ノリの養殖で知られる三河湾は近年埋立てにより東三河工業地帯としての開発が進められいる。
集落の起源は豊川の渡津として起り、中世には今橋と呼ばれ1505年(永正2年)牧野古白の今橋城が築かれ、のち地名は<吉田>と改称し1584年(天正12年)池田輝政15万石の城下となった。この時整然たる城下町が出来上がった。
江戸時代にはさらに東海道五十三次の主要宿駅となり、札木町、本町、上伝馬町が中心街を形成し、本陣、脇本陣、旅籠屋、問屋場等が設けられた。1876年(明治9年)に豊橋と改称された。
東三河平野、或いは東三平野とも呼ばれる。肥豊な沖積平野と洪積台地の段丘面とからなり、前者は水田に後者はもと桑園や陸軍演習地に利用されたが、第2次世界大戦後は果樹園、開拓地となり、景観が一変した。沖積地は江戸時代から新田干拓が行われ、松島(1667年)、加藤(1696年)、青竹(1770年)、富久縞(1821年)、神野(1894年)などの諸新田が作られた。また、段丘上に豊橋市、豊川市をのせている。
輸入車の取り扱いシュアが全国の約50%を占め、日本の輸入基地に成長した愛知県・三河港を、自動車の総合物流拠点にしようという「国際自動車コンプレックス(複合拠点)計画」が、同県豊橋市などや、地元企業の間で進められている。
日本に送り込んでいる欧米メーカーに働きかけて、廃車になった輸入車のリサイクルセンターを共同建設したり、海外からビジネスマンガンが集うコンベンションセンターを設けて、地域活性化を図ろうとしている。
日本のほぼ中間に位置し、近くにトヨタ自動車や三菱自動車、スズキの工場が集積している三河港は、地元の積極的な誘致活動が功を奏して、1990年以降、続々と欧米メーカーの車が陸揚げされるようになった。
周辺には、すでにホルクスワーゲンやダイムラークライスラーなどが、納車前の点検整備を行う新車整備センターを設置している。コンプレックス計画は、この整いつつある物流基盤をもとに、自動車産業の国際的な一大ビジネス拠点を目指している。
廃車のリサイクルセンターや、コンベンションセンターのほかに、国内外の大学が自動車技術を共同研究するプロジェクトも計画、2005年の愛知万博の開催に合わせたモーターショーの開催も検討中だ。
計画に参画する民間シンクタンク、東三河地域研究センターの戸田敏行常務理事は「自動車の売り買いだけでなく、自動車産業を介した国際的な人の交流を生み出し、地域おこしにつなげたい」と意気込む。
そのため、同様の計画を持つ海外の港湾都市と交流を進めている。最近では、中国最大の自動車産業拠点として整備が進む上海市と関係強化を模索中だ。昨年9月、計画を推進する地元の神野信郎・中部ガス会長らが上海市を訪問、今年1月には、上海側視察団が来日、企業誘致などの連携を検討した。神野会長は「地域の自動車産業の発展には、国際的視野が必要だ国際競争にも勝てる世界自動者都市『豊橋』を作りあげたい」と夢を膨らませている。
中心部
市役所、吉田城、美術博物館などの施設があり、豊橋駅を中心に商店街が発達しています。また、駅前から市東部方面へ路面電車(市電)が通り、市民の足として親しまれています。
●路面電車
「市電」の愛称で親しまれる路面電車は、大正14年に駅前~神明~札木間及び神明~柳生橋間が開通。現在は豊橋駅から東部の運動公園、赤岩口を結び、通勤や通学、買い物などに向かう市民の足として活躍しています。札木-東八町間は車の行き交う国道1号線の真ん中を悠然と走ります。
●吉田城跡
吉田城は1505年に築城された今橋城が後に改称されたもので、現在は昭和29年に復興された隅櫓が豊川のほとりに建っています。豊橋公園内にあり、美術博物館、三の丸会館とともに多くの市民に親しまれています。
▼豊橋公園内:今橋町(市電・市役所前下車)
●瓜郷遺跡
約2000年前の竪穴式住居跡が豊川河口にほど近い瓜郷にあります(1953年に国の史跡に認定)。弥生時代中期から古墳時代初期までの集落で、豊川沖積地の湿地を利用した水田が開かれていたと考えられ、標識遺跡として貴重な存在です。弥生時代の出土品と5分の1の復元住居が豊橋市美術博物館に収蔵・展示されています。
▼瓜郷町寄道地内(JR飯田線下地下車・徒歩15分)
●豊橋まつり
毎年10月第3土・日曜日に開催される東三河地区最大のイベントです。カーニバル大行進、市民総おどり、子ども造形パラダイスなど市民参加型の多彩な行事が行われます。 |



 |
東部、南部
総合動植物公園、自然史博物館、地下資源館、視聴覚センター、二川本陣資料館などの文教施設や、岩田運動公園などのスポーツ施設があります。東海の小尾瀬として知られる葦毛湿原は東部丘陵地域に位置します。
戦後開拓された農地には豊かな野菜が実り、農業粗生産額日本一の実績を誇っています。また、国立豊橋技術科学大学を核に産・学・官が連携して地域産業の活性化と技術力の向上を推進する「サイエンスクリエイト21計画」が進められている地域です。太平洋に面する表浜海岸は、アカウミガメの産卵地として知られています。



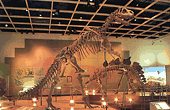

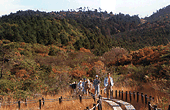
 |
●表浜海岸
▼遠州灘に面して約51㎞続く白い砂浜海岸です。6月~8月アカウミガメが産卵に来ます。4月上旬~11月下旬は地引き網も楽しめます。
●汐川干潟
渥美半島の付け根、豊橋市と田原町に広がる日本最大級の干潟です。約250種類の鳥類や干潟特有の動植物が見られます。
●豊橋総合動植物公園
▼およそ40ヘクタールの広大な敷地内に、自然史博物館、動物園、植物園、遊園地を備えた総合公園です。850種類1400点の熱帯・亜熱帯植物が生い茂る大温室や、ユニークな「モネコーナー」などの植物園ゾーン。アフリカ園、極地動物館などの動物園ゾーンなどなど、子どもから大人まで楽しめる憩いのスポットです。
▼大岩町大穴(豊鉄バス・のんほいパーク下車)9:00~16:30/月・年末年始休園大人600円・小中学生100円
●自然史博物館
豊橋総合動植物公園の一角にあります。約6700万年前の恐竜アナトサウルスの実物化石の展示、豊富な化石資料、ジオラマ、大型映像設備などで地球と生物の歴史を楽しみながら学べるユニークな施設です。
▼大岩町大穴(豊鉄バス・のんほいパーク下車)9:00~16:30/月・年末年始休園大人600円・小中学生100円
●二川宿本陣資料館
東海道筋に現存する貴重な二川宿馬場家本陣遺構を改修復元。新たに建設した土蔵風の資料館とともに「二川宿本陣資料館」として一般公開しています。大名などの身分の高い人が宿泊・休憩した「上段の間」を始め、主家、中庭などが再現され、江戸時代の宿場の雰囲気を味わうことができます。
▼二川町中町(JR東海道本線・二川駅下車)9:30~16:30/月・年末年始休館大人300円・小人100円
●葦毛湿原
「東海のミニ尾瀬」と呼ばれる弓張山系の西側に位置する湿原。湿原内には希少な植物や、三河地方特有の植物が自生し、食虫植物も多く見られます。
ハイキングコースとしても知られ、春から秋にかけて可憐な花が見られます。春はハルリンドウ、ミカワバイケイソウ、秋のシラタマホシクサなど見応え充分です。
▼(岩崎町字長尾(豊鉄バス飯村岩崎線・岩崎下車)
●岩屋観音
江戸時代の聖観音像を昭和25年に再建。奈良時代の僧行基が千手観音を安置したのが起源とされる岩屋観音堂には文化財が沢山残っています。
▼(大岩町火打坂(JR東海バス浜名本線・岩屋観音下車) |
西部
自動車の輸入台数・金額ともに全国第一位を誇る「豊橋港」を中心に臨海工業地帯が形成されています。総合体育館、ライフポートとよはし、市民病院の開院など大きく変貌しつつある地域です。
●みなとフェスティバル
毎年、夏休みの祝日、7月20日(祝)海の日。ライフポートとよはしと三河港神野ふ頭を中心とした会場では、子どもから大人まで楽しめる様々な催しが行われます。
▼(ライフポートとよはし他)
高師緑地
市の南部に位置し、古くは高師原陸軍演習場として使われていた場所で、今日では、緑豊かで、遠足、ジョギングなど、多目的用途に利用されている公園。
所在地:高師町、計画面積:30.47ha、
開設面積:2417ha、開設年月日:昭和42年4月1日
アクセス:豊橋駅より豊橋鉄道渥美線「高師」下車、徒歩3分
●祇園祭
7月第3金・土・日曜日に開催。三河伝統手筒花火発祥の地として知られる吉田神社境内で手筒花火約300本、豊川河畔で打ち上げ花火約12,000本を奉納。夜空を彩る勇壮な花火は、天空にひそむ悪霊を吹き飛ばす最良の方法と伝えられています。豊橋の夏の風物詩として親しまれている祭です。
(吉田神社)
●羽田祭
10月第1土・日曜に開催される羽田八幡宮のまつり。五穀豊穣を祈願して約700本もの勇壮な手筒花火を奉納。東三河地方独特の手筒花火は、火薬を詰めた1本4~5キロの手筒を男衆がからだの脇に抱えもって行われる花火です。ふりそそぐ火の粉とすさまじい爆音。勇猛果敢に挑む姿が感動的です。
(羽田八幡宮)
●神野地区
三河港豊橋エリアの核となる地区で、総面積96haの東地区と111haの西地区からなり、水深-4.5mの内貿用から水深-12mの外貿用までの5種類の公共岸壁が総延長3,000m整備され、700から30,000重量トンまでの船舶が一度に23隻係留することができます。
東地区は公共ふ頭として、各種上屋や倉庫、広大な野積場が整備され、自動車の輸出入をはじめとする様々な港湾活動が活発に行われるとともに、憩いの場所としての公園緑地等の整備も進められています。
西地区は公共ふ頭と工業用地で構成され、大型外貿用岸壁をはじめとする港湾施設の整備が進められる中、平成10年11月神野7号岸壁に「三河港豊橋コンテナターミナル」の運用が開始しました。また、新たな産業立地のために広大な埋立計画が着々と進められており、輸入に対応した海外の企業も進出し、操業を開始しています。
●船渡地区
内貿貨物を扱うために整備された公共ふ頭で、水深-4.5m及び-5.5mの岸壁が11バース整備されており、-4.5mは非常災害時を想定した耐震構造となっています。
また、水際線を利用した緑地等の整備も進められています。
●大崎地区
大崎島の外周を埋め立てて造成したこの地区は659haで、本市唯一の臨海工業地帯として、製鉄所、造船所及び昭和48年から木材住宅関連産業基地として出発した明海地区産業基地で構成されています。
特に、この産業基地は地区全体の約3/2を占め、木材住宅関連はもとより、現在では自動車関連企業や化学関連企業の進出も見られ、活発な生産活動が行われています。
また、原材料及び製品の搬出入のため、企業の専用岸壁も整備されています。 |


 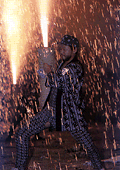



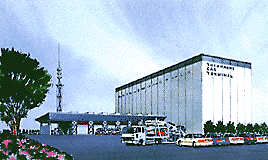
|
北 部
石巻山がそびえ、多くが丘陵地帯です。「石巻の柿」で有名な次郎柿をはじめ、イチゴ、モモ、ブドウなどの果樹栽培が盛んな地域です。最北端には初夏に美しい花しょうぶを咲かせる賀茂しょうぶ園があります。
 ●花しょうぶまつり
●花しょうぶまつり
6月1日~20日賀茂しょうぶ園で開催。約300種類約37,000株の花しょうぶが咲きほこり、期間中はライトアップも行われます。(賀茂しょうぶ園)
●朝倉川とホタル
朝倉川は豊橋市の東部弓張山地に水源を持ち、比較的人口の密集する東部の市街地を西方に流れ、豊川下流部に注ぐ流域面積17k㎡、流路延
 長8.63kmの一級河川です。
長8.63kmの一級河川です。
朝倉川の改修は昭和41年10月12日の水害を契機に実施されました。改修以前は流域の大半が山林と水田地帯となっていたため、水量も多く、多くの水生生物が生息し、ホタルの飛び交う自然溢れる姿がありました。昭和41年の洪水を契機に行われた災害復旧事業及び中小河川改修事業、柳生川水系内山川の朝倉川への流路変更や昭和44年に始った豊橋市多米土地区画整理事業などにより、流路や流量、護岸形態が大きく変容しました。
シソの植物学
花穂(はなほ)は、主に刺身の「たてつま」として利用されています。みなさんは、花穂をお刺身の横に付いている「飾り」と思っているのではないでしょうか?
つま野菜というのは、単なる「飾り」ではなくて、基本的に食べられるものなんです。色や形などの見た目の美しさだけでなくその香りや味でも、主役の刺身を引き立てているんです。花びらをちょっとつまんで、醤油に入れるとほのかにいい香りがたってきます。
花穂は、
シソの「香り」と「いろどり」を添えてくれます。また、花穂は、刺身の「つま」以外にも、そうめんの薬味や椀物、てんぷら、などなどいろいろな使い方があります。
シソは、ヒマラヤ、ビルマおよび中国の原産といわれ、東洋の温帯地帯に広く分布している。
我が国へ伝わったのはかなり古い時代であり、イヌエ、ヌカエ、ノラエなどと呼ばれ、薬科とか漬け物として利用されていた。
シソは、1年生の草本で、茎や葉など全体に芳香があり、その若葉や花穂は、香辛料や交品として利用されている。葉は対生し、心臓型で縁辺は鋸歯状をしている。茎は四角で色沢によって赤ジソ・青ジソに分けられ、さらに、葉面が平滑なものとちりめん状のものがある。
短日性植物で、枝上の葉腋に長い花茎を直立に抽出し、淡紅色・白色または桃色の小さな唇形の花を房状につける。花柱は先端で二裂する。果実は、一個づつの種子を持つ四つの小分果があり、成熟すると裂開して離脱する。種子は、球形か短卵形をしている。
しそ(紫蘇)は、古くから日本で栽培されてきました。初めは薬用とされ、葉は、気を通す
芳香健胃薬として食欲増進、毒消しに、また風邪薬として他の生薬と配合して使われるとき
には発汗作用に、種子は喘息など咳の多い症状に使われます。戦国時代の朝鮮征伐の時、加
藤清正は、部下の士気の低下をこの紫蘇の入った漢方薬「香蘇散」でなおしたといいます。
こういう使いかは「気剤」といい、現代的な抗うつ剤のない昔は芳香のある生薬で、ウツウ
ツとした気を紛らわせていたのでしょう。
また、最近では、しそに抗酸化物質のルテオリンやα-リノレン酸が、多く含まれていること
がわかり、現代病のアトピーやアレルギーの改善に有効であることがわかってきた。
ルテオリンや α-リノレン酸、そして、しその香り(ペリラアルデヒド)については、次の
項目で説明します。
フラボノイドの一種で、抗酸化力が最も強い部類に入ります。フラボノイドは、ポリフェノール化合物の中の一群の総称で、植物の葉や根、茎、花、果実などあらゆる器官に存在しています。
その種類は、4,000以上にもなります。化学構造の違いにより、フラボン、フラボノール、イソフラボン、カテキン、アントシアニジンなどに分類されます。
ルテオリンはシソの種子に豊富に含まれるフラボノイドです。
ルテオリンは、セロリやピーマン、春菊、カモミール、などにも含まれますが、シソの種子に含まれているものは、特殊な形体をしていて、はじめから糖がついていないアグリコンの形で
存在しています。
普通、
体に吸収される過程で配糖体の場合は腸管で糖が切れてアグリコンになってから吸収されます。 シソの種子に含まれるルテオリンは、もともとアグリコンなのでそのまま吸収されます。肝臓で水溶性の形にしてしまうのですが、水溶性の形になってしまうと抗酸化力や生理活性が落ちてしまいます。しかし、シソの種子に含まれているルテオリンは、水溶性の形にならずにアグリコンのままで存在していて、生体内でより高い抗酸化力や生理活性を発揮すると考えられています。
現代社会は、ストレスや大気汚染、食生活の変化などによって体内で活性酸素(フリーラジカル)が、増加しやすくなり、心疾患など酸化が原因の疾病も増えていますが、ルテオリンは、これらの身体に悪影響を及ぼす活性酸素を強力に撃退する力を持っています。
また、花粉症やアトピー性皮膚炎をはじめとするアレルギー性疾患に対してもよい影響を示しています。ルテオリンはアレルギーにいたる酵素作用を阻害する働きがあります。フラボノイドには、同様の阻害作用を示すものもありますが、一番強い効果を示すのはルテオリンだというデーターも存在します。
ルテオリンなどのフラボノイド類は、毎日の食事で摂れる成分であり、健康の維持に重要な役割を持った栄養素です。毎日野菜などを食べるようにすると、常にある程度のフラボノイドを体内にとどめておくことが出来ます。そして、現代を生き抜いていくためにも毎日野菜を食べるようにしましょう!!。
シソの実を「ほじそ」と呼んでいます。関東や関西などでは、呼び名が「束穂(たばほ)」、「花穂(かほ)」、花のことを「ほじそ」などと、いろいろと誤解を招くことがありますが、ご配慮願いますようにお願いします。
シソには大変強い香りがあります。主にペリラアルデヒドという成分がそうです。殺菌作用や防腐効果があると言われています。生魚や料理に添えられた大葉や花穂、ほじそには昔からの生活の知恵があるのです。
江戸時代の有名な浮世絵師広重の作品で、「魚づくし」の中の一枚です。題目は、「すずき・金目鯛にしそ」です。すずきや金目鯛の季節にふさわしい植物としてシソが添えられています。
方言の数々
| 言葉(方言) |
意味・用例 |
言葉(方言) |
意味・用例 |
| いじゃ |
いっしょに行こう。さあ、行きましょう。 |
ひずるしい |
まぶしい。 |
| おし |
君。あなた。 |
こないだ |
この間。この前。先日。 |
| おしんち |
あなたの家。 |
~かん |
~ですか。~じゃないですか。 |
| わしゃが |
私の家。 |
こんぼう |
(動物の)子ども。 |
| けなるい |
うらやましい。 |
ちゃっと |
急いで、すぐに |
| ~りん |
~しなさい。 「出かけるで、ちゃっと片づけりん。」 |
| ちんちん |
(お湯などが)すごく熱い様子。 「お茶がちんちんで舌べらやけどした。」 |
| ぼっくう |
いたずら。 「ぼっくうするな。」「ぼっくう小僧」 |

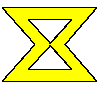 市のマークの由来
市のマークの由来






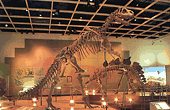

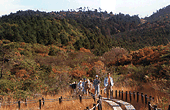




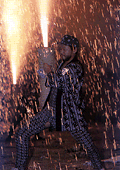



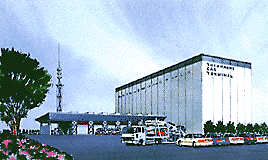
 ●花しょうぶまつり
●花しょうぶまつり 長8.63kmの一級河川です。
長8.63kmの一級河川です。